チーム医療が重要となる糖尿病治療を中心に
患者に寄り添う医療を提供
2024年4月に、市立東大阪医療センターの内分泌・代謝内科部長として就任された平田先生。高齢化が進む現在にあって増加している糖尿病の治療を中心とする同診療科の現状と展望についてうかがった。
内分泌・代謝内科の現状
医療従事者や地域を含め強固なチーム体制を構築
市立東大阪医療センターの内分泌・代謝内科では、糖尿病のほか、甲状腺などホルモンの内分泌疾患、コレステロールや中性脂肪といった脂質代謝異常を中心に、地域のクリニックから紹介を受けた患者の治療にあたっている。「私が赴任する前まで、川口内科統括部長が長年に渡って積み上げてこられた土壌を引き継ぎながら、医療の進歩や患者さんそれぞれの生活にあわせて新しい診療や体制づくりを進めています」と話す平田先生。高齢化が進む現在では、糖尿病患者が増加傾向にあり、血糖値を下げるという以前までの治療だけでは対応が難しくなってきている。「糖尿病は、治療することによって疾患がゼロになるという病気ではなく、長期間向き合っていかなければならない病気です。以前と比べて注射の種類も変わってきていますし、糖尿病に起因する合併症も増えてきていますので、患者さん個々に応じた治療を行っていく必要があります」。長年に渡って向き合っていく疾患という特徴から、治療に関しても医師一人だけではなく、看護師、栄養士、リハビリテーションなどの各スタッフのほか、地域医療機関や患者のご家族との連携が重要になってくる。「当センターの内分泌・代謝内科は、私を含めて3名の医師で対応していますが、外来患者に加えて、ほかの疾患でセンターに入院されている患者さんの糖尿病治療にも対応していますので、マンパワー的に不足している状況です。スタッフの補充はもちろんですが、センター内の医療チーム、地域医療機関、患者さんのご家族と3つの強固なチーム体制を構築して、可能な限り患者さんに寄り添った診療を提供していけたらと考えています」。

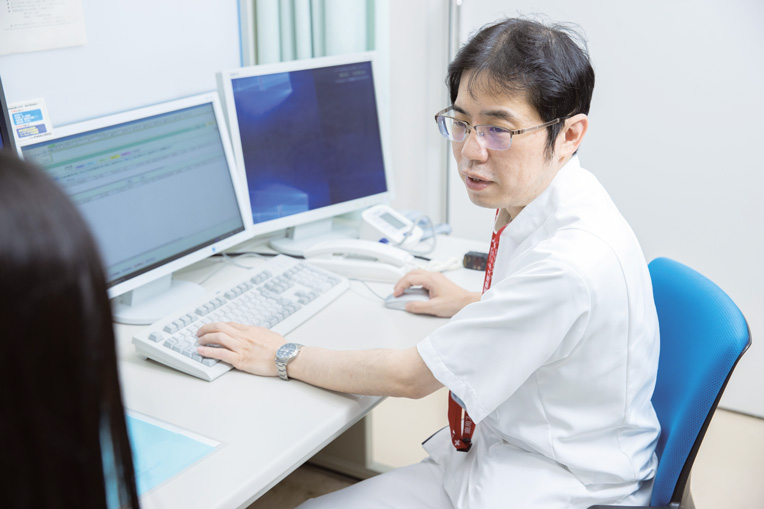

ほかの診療科との連携
血糖値をコントロールしほかの診療科につなげる
入院患者の中には糖尿病を患っている方も多く、ほかの疾患の治療を行うためには血糖値のコントロールが不可欠なため、内分泌・代謝内科はほかの診療科と連携する機会が多くなる。「様々な診療科と連携する機会が多いことから、内分泌・代謝内科分野だけでなく、連携する他の診療科についても幅広い知識のアップデートが必要になってきます。私たち内分泌・代謝内科の役割は、ゲートキープを果たしてほかの診療科につなげていくことだと感じています」と平田先生。医局が一つに集約されている同センターは、ほかの診療科との連携を密にするために最適な環境。複雑化する疾患に対して、より円滑な治療を提供していくための平田先生を中心とした取組みは続いていく。内分泌・代謝内科の魅力として、患者と深くじっくりと長く向き合っていけることと話す平田先生。治療する側とされる側という立場ではなく、医師と患者が一緒になって治療していくことを大切にしている。「糖尿病になることで、自分の体に向き合えるようになったというプラスの面を強調しながら、前向きに共に治療していけたらと思います」。

今後の展望と想い
地域医療機関との連携強化 住民への教育にも尽力
地域医療機関との連携強化のために、様々な会に参加して要望をヒアリング。病棟の運用も含めて、体系的な組織づくりにも尽力している。「今後はもっと地域からご紹介いただく患者さんを受け入れられればと考えております。低血糖が疑われる糖尿病患者に対しての2週間の持続血糖測定のほか、話題となっている肥満症などにも積極的に対応していきます。また、地域住民に対しては、当センターの講堂で月に2回教室を開催しています。食事の話など有益な情報を提供していますので、お気軽に利用いただければと思います」。平田先生の精力的な取組みが、東大阪の医療を向上させていくに違いない。

