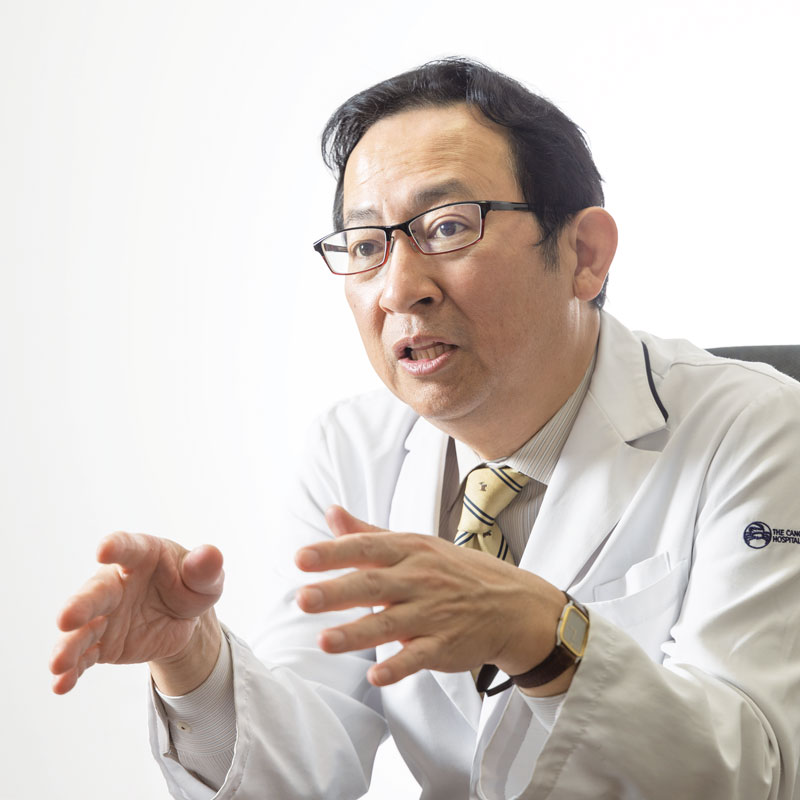担当医
朝子 幹也 病院教授
関西医科大学総合医療センター耳鼻咽喉科・頭頸部外科部長/関西医科大学卒/医学博士、日本耳鼻咽喉科学会専門医・専門研修指導医、日本アレルギー学会専門医・指導医・代議員/アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎の手術治療に精通。各種ガイドラインの作成にも携わる
[テーマ]
直腸がんに対する肛門温存手術の進歩
より肛門に近いがんでも肛門温存が可能に
大腸の肛門に近い部分に発生する直腸がん。1980年代以前は直腸がんを肛門括約筋ごと切除し、人工肛門を設ける治療法が一般的であったが、1980年代以降は自動縫合器の誕生や医療技術の進歩により、肛門に近い位置に発生したがんであっても、がんの前後で腸を切除し縫合することで肛門を温存する治療が可能になったという。「さらに近年は当院をはじめとした専門施設において、直腸がんとともに内肛門括約筋を切除する括約筋間直腸切除術が行われるようになりました。肛門括約筋には無意識的にお尻を締める内肛門括約筋と、便意を我慢するなど意識的にお尻を締める外肛門括約筋があります。この治療法により肛門を温存しつつ、さらに肛門に近い位置のがんも取除くことができるようになったのです」と福長教授は教えてくれた。

従来よりも精緻な手術を可能にした手術支援ロボット。肛門近くのがんでも直腸と内肛門括約筋を切除し、人工肛門を回避できる
患者の状況や希望に合わせ最適な治療法を提案
人工肛門に抵抗がある患者にとって、有効な治療法である括約筋間直腸切除術。しかしそのリスクもしっかりと理解した上で、治療法を選択する必要があると福長教授は話す。「例えば高齢者の場合、肛門括約筋が弱っている可能性が高く、治療後に排便をうまくコントロールできず、便が漏れるなどの症状が出やすくなります。また寝たきりなど
介護が必要な方の場合、人工肛門の方が管理しやすいという点もあります。ほかにも外出機会が多い方や仕事で長時間の会議に参加する方などは、便漏れや頻便が生活や仕事に支障を及ぼす場合もあります。当院ではがんの位置や進行度に合わせて治療法をご提案し、治療後の生活スタイルや患者さんの希望に寄り添いながら、最適な治療法を見つけ出していきます」。また福長教授の就任以降、進行下部直腸がんに対する集学的治療として、抗がん剤治療や放射線治療を組み合わせた治療を導入。「進行がんの場合、手術前に放射線治療を行いがんを縮小できれば、侵襲の少ない手術が可能になります。また放射線治療によって肉眼的にがんが見えなくなることがあり、手術をせず経過をみるという究極の肛門温存を選択されるケースもあります」。
_03.jpg)
抗がん剤治療や放射線治療の実施においては、副作用を考慮した上での適応の有無について情報共有を行うなど、医療スタッフの教育にも尽力
_04.jpg)
全がん患者の95%以上に腹腔鏡下手術を実施。腹部に小さな穴を開けて腹腔鏡を挿入し行う手術のため、開胸手術に比べて身体への負担が少ない
大腸がん治療の情報を発信医療施設との連携を図る
食道から大腸までの消化管全般の診療の経験を経て、年々増加する大腸がんの治療の重要性を認識し、その研究と治療に長年尽力してきた福長教授。「大腸がんは専門施設での高度な治療が求められる領域です。しかし早期に発見し適切に治療すれば、治癒する確率も高くなります。そのため便秘や下痢を繰り返すなど、日常生活の中
で少しでも異変を感じることがあれば、ためらうことなくまずは検査を受けていただきたいです。内視鏡検査に抵抗がある方も多いかと思いますが、近年は検査機器や医療技術が進歩しているほか、状況によっては鎮静剤を使って眠っている間に検査を終えることも可能です」。また患者一人ひとりに合わせた最適な治療を提供できるよう、周辺の医療機関との連携強化にも尽力。福長教授自ら足を運び、同院で対応可能な治療法についてなど情報共有を積極的に行っている。「地域のクリニックや病院で大腸がんと診断された方が安心して専門的な治療を受けられるよう、引き続き周辺の医療機関との信頼関係を築いていきます」と力強く語る福長教授。専門性の高い大腸がんの治療法について広く発信し、地域連携の輪を広げていく。
専門医療にできること!
専門医療にできること-318x1024.jpg)